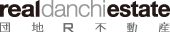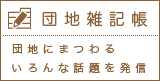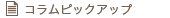公団設立とともに入社し、崇高な思想と素晴らしいデザインで活躍した津端さんは、その20年後に勇退。
以来40年、広いキッチンガーデンのある小さな家でこつこつと「ときをためる暮らし」をしてきました。
そんな津端さんの最晩年を追った映画が、2017年1月2日より劇場公開されます。

名作団地の数々を残した津端修一さんと、奥さんの英子さん。
津端修一さんの名前は、団地好きなら一度は聞いたことがあるかもしれません。
あるいはその名前に聞き覚えがなくても、伝説の団地、阿佐ヶ谷住宅のことなら知っているはず?
他にも、多摩平団地や、赤羽台団地、高根台団地など。手掛けた団地は、どれも名作と呼ばれるものばかり。
そうそうたる名前が並びます。
そんな津端修一さんと、奥さんの英子さんの暮らしを追ったドキュメンタリー映画がこの『人生フルーツ』。
2015年6月に修一さんが90歳で亡くなられる前後の、2年間の日常がつづられています。

雑木林に囲まれた大きなキッチンガーデンのある小さな家で40年間暮らしてきました。
そんな津端さんですが、実は団地以外でも有名なご夫婦。
雑木林に囲まれた大きなキッチンガーデンで、70種類もの野菜と、50種類もの果物を育て、自家製のジャムやベーコンを作りながら、ゆっくりと暮らしを楽しんできたそのライフスタイルは、いくつもの女性誌や数々の書籍などで紹介されてきました。
「ときをためる暮らし」と表現されるその日々は、今ではすっかり注目の的になっているスローライフの、まさに先駆けともいうべきもの。それを40年も前から実践しているとあれば、メディアが放っておくわけがありません。
なので、団地を知らずとも、津端さんの存在が気になっていたという方も、きっと多いのかなと思います。

自宅は師であるアントニン・レーモンドの家に倣ってつくられた30畳のワンルーム。
でも実は、ずっと疑問に思っていたのです。
名作団地の数々を手掛けたスター建築家としての津端さん。
そして、広い庭のある小さな家で、ゆっくりと自分の暮らしを楽しむ津端さん。
どちらも憧れの存在ではあるけれど、重なりそうでピタリとは重ならない、二つの像。
片や団地は当時、国家をあげたプロジェクトとして社会に多大な影響を与えた仕事。片やまるで世の中と隔絶するかのように、雑木林の中にこもり自分の暮らしとていねいに向き合う日々。
その二つはどう結びつくのだろうかと、かねてから不思議に思っていたのです。そこにひとつのヒントを与えてくれたのが、この映画でした。

笑顔がかわいい津端さんですが、ちょっと気難しくて、意外と鋭く、頑固で、変な人。その魅力を描きたかったという監督。
全国に団地をつくるため、1955年に設立された日本住宅公団。その創設メンバーとして津端さんは入社します。
大学では丹下健三の教えを受け、卒業後は前川國男の紹介でアントニン・レーモンドの事務所に入り、その後、坂倉準三の事務所を経て公団へ。まさにエリートという言葉がピッタリの津端さん。
公団では数々の実績を残していますが、団地全体の配置デザインを多く手掛けた津端さんは、その作風から「風土派」と呼ばれるようになり、その思想は後の団地設計に大きな影響を与えます。
それは団地を建てる前の自然地形を壊さずにそのまま残し、その記憶を住まい手に伝えていこうというもの。「自然と人間の関係を問い直す」ということを意識していたのだと、後に津端さんは語っています。
そんな思想に基づいて、数々の素晴らしいデザインを残した津端さん。
ですが、団地の設計において、いわば“原案”ともいうべき津端さんのデザインは、実際の建設までに変更を余儀なくされ、当初の思想とは異なる形で建設されるということがしばしば起こります。というよりも、むしろほとんどの現場において、崇高なその思想は理解されず、丘を削り、谷を埋め、木々を切って、更地にして建設をするという方法が選ばれる、ということが起こるのです。

生まれ故郷である愛知県に移り、高蔵寺ニュータウンのマスタープランを手掛けた津端さん。
そんな憂き目ともいえる状況が続いた津端さん。
そして時代の変化も相まって、さらに逆風が強まります。
高度経済成長によって都市部に集中した人たちに、住む場所を確保するためつくられた団地。しかし、その供給を担っていた公団に、もうひとつの役割があったことは、あまり知られていません。
それが「ライフスタイルの革命へのチャレンジ」であったと津端さんは語っています。
当時、衛生面でも環境面でも良好とはいいがたかった一般市民の生活。それを、西洋諸国に劣らない水準まで押し上げ、豊かな生活環境を提供すること。そのためのデザインや設備、構造、工法などの追及が、初期の公団に課せられた重要なミッションでした。
そして、それこそが津端さんを公団へと入社させた、最大の動機だったのです。
名建築家たちのもとで学び、海外の建築事情にも精通していたという津端さん。そんな彼が公団への入社を選んだ理由を、後にこんな風に語っています。
「当時、戦後の最高の技術を見て、それを市民にプレゼントしたいと思って僕は公団に入った」のだと。
しかし、そんな高い志で団地をつくろうとする津端さんの気持ちとは裏腹に、1970年代に入る頃には予想を上回るペースで都市部の人口が急増、公団は住戸供給数のノルマ消化に追われるようになっていくのです。

大きなキッチンガーデンでは、70種類もの野菜と、50種類もの果物を育ててきました。
そんな逆風が特に強かった東京に見切りをつけ、新天地を求めた津端さんが選んだ仕事、それが生まれ故郷である愛知県の高蔵寺ニュータウンの建設でした。そして、後にその一画に土地を手に入れてつくったのが、この映画の舞台になっている大きなキッチンガーデンのある小さな家です。
メディアで取り上げられることも多い、その暮らし。若い女性も憧れる理想のライフスタイルに浸ろうと、待ち構えていた気持ちはしかし、上映が始まるとしばしその居場所を失うことになります。
うっそうと茂る雑木林の中をカサコソと歩き回り、寡黙に畑仕事をする老夫婦。女性向けのメディアで露出していた、キラキラと光をまとった姿とは少し違う二人がそこにいました。
実は、取材を始める段階では自分もキラキラしたおしゃれなおじいさん・おばあさんとして見ていたという伏原健之監督。しかし、音楽を付けるため編集をした映像を見て、自分が追いかけてきた本当の津端さんの姿とは違うものを作りかけていることに気づき、急きょ編集をし直し、新たに撮影したカットも加えて、できあがったのがこの作品なのだといいます。
人づきあいが苦手だった津端さん。取材をされることも好まず、この映画の取材依頼も当初は完全シャットアウト。4カ月も粘った末に、やっと受けてもらえたのだそうです。
それは雑誌などで見る“ニコニコしたかわいらしいおじいさん”という姿とは異なり、ちょっと気難しくて、意外と鋭くて、変なところもあって、けっこう頑固で、でもとても知的なおじいさん。そんな色んな面を持った津端さんに人間としてのかわいらしさを見つけ、それを描きたかったのだと伏原監督はいいます。
そして、こんなことも。
取材が大嫌いな津端さん。けれど折に触れてメディアの取材を受けてきたのは、自分からは何も言わないけれど、そこに伝えたいものがあったからなのだろう。そして自分も何かを伝えてくれそうだと期待されたからこそ、取材を受けてもらえたはずだ、と。
その撮影は2年間、延べ100日にも及んだそうです。

修一さん、英子さんご夫妻と過ごした時間を語ってくれた伏原健之監督。
団地の仕事では、崇高ではるか未来を見据えたその思想が理解されず、日の目を見ないプロジェクトも多かった津端さん。でもその仕事について、こんな風に語っています。
「できた、できなかったなんていうのは、その時代と僕たちの力関係の中で決まることで、一時的なことに過ぎないと僕は思う」と。
キッチンガーデンでの暮らしについては、自らあまり語ろうとしなかったという津端さん。
取材をした伏原監督も、自分がそこから感じ取れていないものや、理解できていない本質が、まだまだあるのだろうと語ります。それはもしかすると時間を経て理解できるようになるものかもしれない。そして、そのときに初めて津端さんの先見性に気づけるのかもしれない、と。
でも伝わったかどうか、それは大事なことではないと、きっと津端さんは言うのでしょう。
次の世代のことを考え、何かを残していこうとすること、それが大事なのだと。
そう思ったときに、この映画のタイトルになっているフルーツという言葉が、スッと入ってくる気がしたのです。それは津端さんの人生を彩った果実でもあるけれど、未来へとつなぐ種子を入れる器でもあるのだと。果実はいつか、ポトリと地面に落ちて、そこから新しい芽が生まれ、そしてまた実をつける。それこそが、津端さんが僕らに残してくれたプレゼントなのでしょう。
そう思ったとき、団地の津端さんと、キッチンガーデンの津端さんが、ピタリと重なった気がしたのです。
映画は2017年1月2日から東京・ポレポレ東中野でロードショー、ほか全国順次公開されます。
津端さんからのプレゼントを、多くの人が受け取ってくれるといいなと思っています。
映画の公式サイトはこちら。
映画『人生フルーツ』公式サイト